今回は、落合陽一さんの著書『0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書』を参考にしています。
多くの子どもが感じるであろう、『この教科頑張っても、社会で役立つんだろうか』と言う疑問について学んだ事を、物語風に作ってみました。
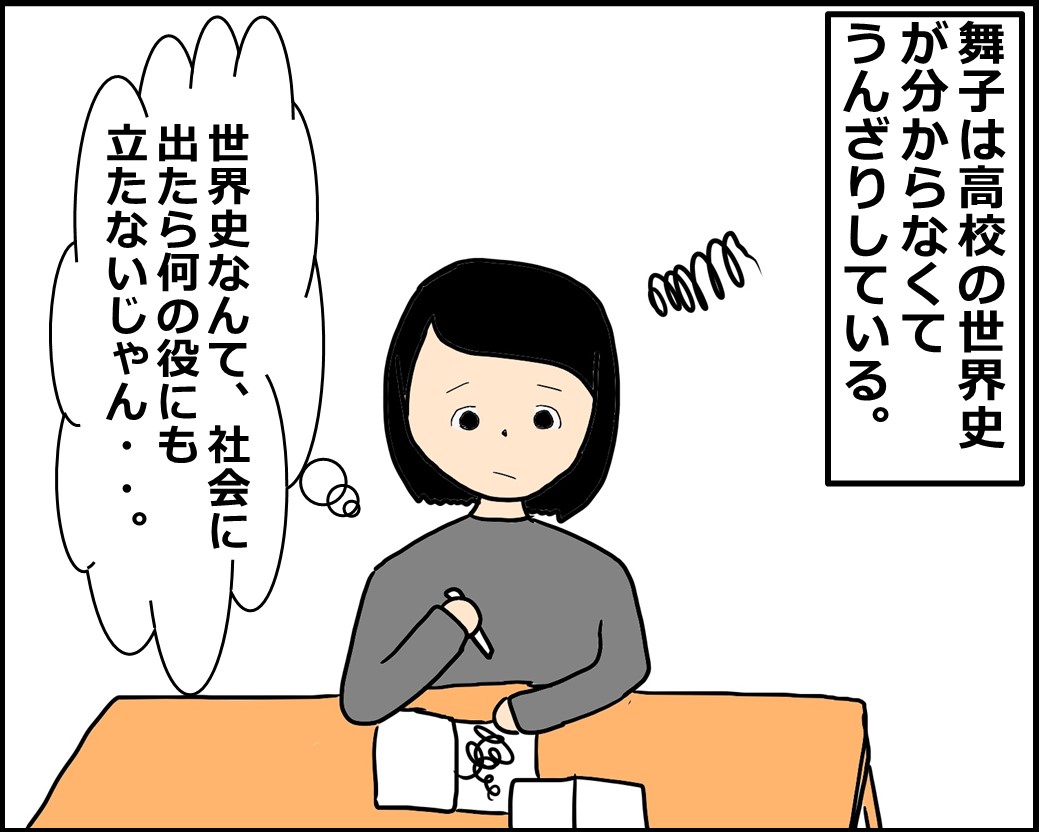




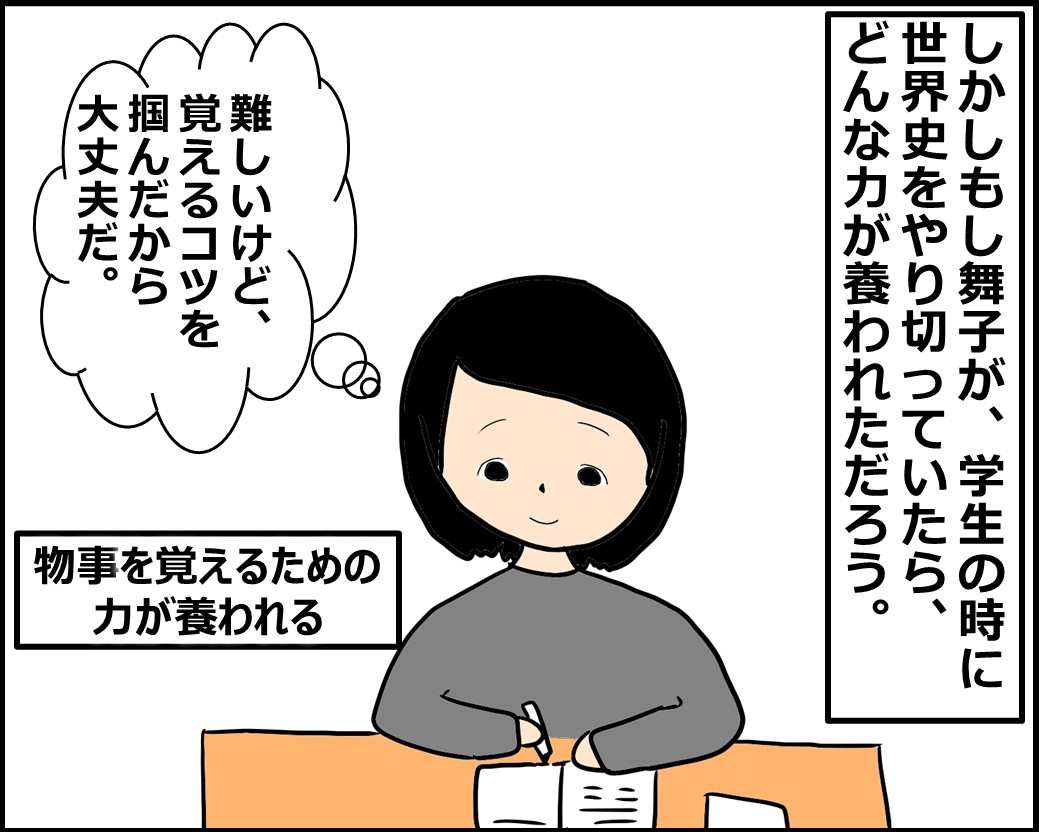



学校の勉強は、学びのトレーニング
落合さんは、自著で次のように言っています。
「学校の勉強なんて社会に出たらまるで役に立たない」とよく言われますが、その考え方の大きな間違いは、教育にある「コンテンツ」と「トレーニング」という2つの要素のうち、後者のもつ意味を正しく認識できていないことです。学校で学ぶ数式や漢字(コンテンツ)も大事ですが、それ以上に学習する訓練(トレーニング)を怠っていたら、社会に出た時に新しいことを学習する方法がわからずに、自分の経験を使えない人となってしまうのです。
私はこの部分を読み、学校で勉強する理由は、学ぶ力を養うためのトレーニングが主目的であることに気付きました。
舞子がもし世界史をがんばっていたら
舞子がもし高校時代に世界史をやり切っていたら、どんな力が養われていたでしょう。例えば工夫して覚える力が身についていれば、社会人になって同じことで何度も注意されることは少なくなったのではないでしょうか。
また、多少苦手なことでも取り組み続ける集中力や、苦手なことでも成果を出す力が養われることで、どんな仕事でもある程度高いクオリティで成果を上げられることができるのだと想像できます。
またテストと言う期限までに、知識を身に付けたり効率よく学ぶ力がつくことで、期限内にサラリと仕事を終わらせるような力が養われるのだと思います。
むすび
私は高校時代、文系科目がかなり苦手でした。しかし社会人になってからも苦手なことはもちろんやってきて、それをこなさなければならない状況と、学生時代の苦手な勉強とはとても似ていると思いましたし、それをいかに楽しく効率的にこなすかについては、もっと学生時代に鍛えることができたなぁと思いました。過去は戻ってこないので、今からでも学びのトレーニングを意識していきたいと思います。
参考にさせていただいた本
0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書(落合陽一さん著)